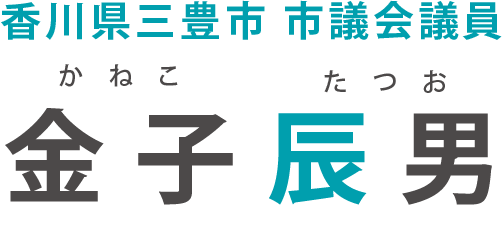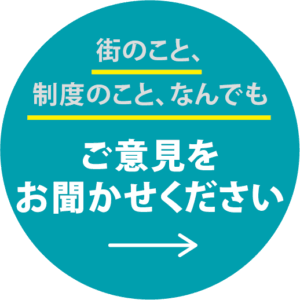⇒ 2025年度 議会活動
令和7年第1回定例会(第3日)一般質問 【2025年03月07日】
・国内カロリーベース自給率38%(R5)。香川県は34%(麺文化等で米消費少)。
・県の水稲作付は10年前比約3割減。米価はH25→R5でほぼ横ばいだったが、R6産は在庫減で高騰(全銘柄平均25,927円/60kg、前年比月次最高水準、前月比+69%)。
・米価上昇は作付拡大・継続意欲に追い風。R6は21地区で地域計画づくりを進行、世代継承を図る。
・三豊は多品目・高品質が強み。AI・スマート農業で収量安定・高品質化・省力化を加速し、稼げる農業へ転換。
・圃場整備率:H19末45.2% → R4末51.0%(+5.8pt、約20ha進捗)。
・地域の合意形成や換地処分に時間と労力を要するが、県営事業が進行。補助率上昇も追い風に、計画的に強化。
・R5改正の農業経営基盤強化促進法で法定化。
・旧小学校区を基準に21地区で座談会を開催、農地の将来像・担い手を合意。
・R6末策定を受け、実行段階へ移行。
【金子議員の質問&意見】要点:いまが転換点。圃場整備×スマート農業×適正価格で“もうかる農業”へ。行政は農家を裏切らないスピード実行を。
・R7/2現在、外国人市民1,392人。主要国:ベトナム415/インドネシア288/ミャンマー196/フィリピン144/カンボジア109/中国101など。
・人口動態:R5は629転入・463転出で転入超過。H27598→R21,043→現在1,392と増加基調。
・在留資格は技能実習等が7割超(1,041人)。
・宿泊者数:R271人 → R5966人に回復。
・免許保有:県警把握で約260人(国別非公表)。
・人身事故:R42件/R51件/R65件。
・65歳以上17人(介護保険の認定・支援利用は近年なし)。
・生活保護1人。
・子ども就学:保育所10/認定こども園9/幼稚園1/小9/中5=計34人。
・保育料・授業料は日本人と同様(3~5歳と義務教育は無償)。
・日本語指導の充実や共同学習で共生を促進。
・7か国語生活ガイドブックを作成(R3アンケートに基づき必要情報を整理、約730部配布)。
・人権課連絡先を明記し、管理団体・企業・窓口経由で配布継続。
・基本的人権は在留外国人にも等しく及ぶ。
・三豊市人権尊重のまちづくり条例のもと、相互理解と生活ルールの周知を進め、共に働き・学び・暮らす社会を推進。
【金子議員の質問&意見】要点:安全・安心の両立。外国人には生活ルールの明確化と伴走支援を、日本人には情報提供と理解促進を。周回遅れの施策ではなく、課題先取りの設計を。
令和5年第1回定例会(第3日)一般質問 【2023年03月08日】
令和5年第2回定例会(第2日) 一般質問 【2023年06月09日】
国が掲げる構想は、デジタルを活用して地方の課題を解決し、地域の魅力を高める取組。
しかし三豊市の目指すデジタル化は、都会との格差をなくすことではなく、市民が住み慣れた場所で健康に、幸せを感じて暮らし続けられるようにするためのもの。
弱い部分をデジタルで補い、持続可能なまちをつくる視点で進める。
・AI人材育成拠点「MAiZM」を設置し、香川高専詫間キャンパスからAIを学んだ学生がベンチャー企業2社を設立。
・教育現場ではオンライン授業やデジタル教育環境の整備を実施。
・地域通貨「MitoPay」導入により地域消費を促進、今後は健康ポイントなどの仕組みへ展開。
・介護MaaS、オンデマンドモビリティなど交通・福祉分野にもデジタル活用を広げている。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・MitoPay登録者数は6,490人(2022年8月末時点)。
・MAiZM起業者は現在学生本人のみで、雇用発生には至っていない。
国の「農業DX構想」に基づき、AI・IoT・ロボット技術導入で作業を効率化。
労働力不足・高齢化の課題を補い、データを活用した消費者志向の農業を進める。
地方の個性を生かした持続可能な田園づくりを目指す。
・スマート農業=省力化・自動化・機械導入による効率化
・デジタル農業=データ収集・共有により経営と品質を安定化
三豊市では両面を組み合わせた取組を推進中。無人車・ドローン導入なども進む。
【金子議員の質問&意見】要点:デジタル=効率化+データ共有。技術と知見の融合で持続的な地域農業へ。
・交付率:42.43%(2022年8月時点)
・窓口キオスク端末導入を準備中(記入不要で証明書発行)。
・引越しワンストップサービス(2023年2月開始予定)で転出入手続をオンライン化。
・出張申請・休日開庁・商業施設での受付など普及活動を継続。
・カード取得が目的ではなく、市民サービス向上のために活用策を検討中。
【金子議員の質問&意見】要点:利便性向上に重点。オンライン化・出張対応で交付率アップを図る。
鶴岡サイエンスパークは産官学民が連携した成功例。
香川県にも高松空港跡地の「インテリジェントパーク」があり、類似の取組が進んでいる。
コロナ禍で働き方や研究の在り方が変化する中、デジタル×田園による新たな産業立地を検討する。
【金子議員の質問&意見】要点:産学官+市民連携による「三豊版サイエンスパーク」構想を視野に。
世代を超えたデータ活用は重要。国の基盤構築を踏まえ、三豊市独自のデータ集積と利活用を検討。
データ連携で市民・企業双方が使える社会を目指す。
デジタル化の目的は「幸福度の向上」。
住み慣れた場所で健康に暮らし続けられることを支える仕組みを整備し、データを活用して幸福感を実現していく。
【金子議員の質問&意見】要点:市民生活に“データの見える化”を。三豊市版ウェルビーイングを指標に進める。
都会と肩を並べるためではなく、三豊市に足りない部分を補うためのデジタル化。
市民が健康で幸せに暮らすことが最終目的。データを整え、市民へ還元するための基盤整備に時間をかけて進める。
デジタル化は“目的ではなく手段”。幸福度を高めるための道具として推進していく。
【金子議員の意見】要点:デジタル万歳ではなく、「幸福のためのデジタル」。データ基盤整備を最優先に。
令和5年第3回定例会(第2日) 一般質問 【2023年09月07日】
国が掲げる構想は、デジタルを活用して地方の課題を解決し、地域の魅力を高める取組。
しかし三豊市の目指すデジタル化は、都会との格差をなくすことではなく、市民が住み慣れた場所で健康に、幸せを感じて暮らし続けられるようにするためのもの。
弱い部分をデジタルで補い、持続可能なまちをつくる視点で進める。
・AI人材育成拠点「MAiZM」を設置し、香川高専詫間キャンパスからAIを学んだ学生がベンチャー企業2社を設立。
・教育現場ではオンライン授業やデジタル教育環境の整備を実施。
・地域通貨「MitoPay」導入により地域消費を促進、今後は健康ポイントなどの仕組みへ展開。
・介護MaaS、オンデマンドモビリティなど交通・福祉分野にもデジタル活用を広げている。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・MitoPay登録者数は6,490人(2022年8月末時点)。
・MAiZM起業者は現在学生本人のみで、雇用発生には至っていない。
国の「農業DX構想」に基づき、AI・IoT・ロボット技術導入で作業を効率化。
労働力不足・高齢化の課題を補い、データを活用した消費者志向の農業を進める。
地方の個性を生かした持続可能な田園づくりを目指す。
・スマート農業=省力化・自動化・機械導入による効率化
・デジタル農業=データ収集・共有により経営と品質を安定化
三豊市では両面を組み合わせた取組を推進中。無人車・ドローン導入なども進む。
【金子議員の質問&意見】要点:デジタル=効率化+データ共有。技術と知見の融合で持続的な地域農業へ。
・交付率:42.43%(2022年8月時点)
・窓口キオスク端末導入を準備中(記入不要で証明書発行)。
・引越しワンストップサービス(2023年2月開始予定)で転出入手続をオンライン化。
・出張申請・休日開庁・商業施設での受付など普及活動を継続。
・カード取得が目的ではなく、市民サービス向上のために活用策を検討中。
【金子議員の質問&意見】要点:利便性向上に重点。オンライン化・出張対応で交付率アップを図る。
鶴岡サイエンスパークは産官学民が連携した成功例。
香川県にも高松空港跡地の「インテリジェントパーク」があり、類似の取組が進んでいる。
コロナ禍で働き方や研究の在り方が変化する中、デジタル×田園による新たな産業立地を検討する。
【金子議員の質問&意見】要点:産学官+市民連携による「三豊版サイエンスパーク」構想を視野に。
世代を超えたデータ活用は重要。国の基盤構築を踏まえ、三豊市独自のデータ集積と利活用を検討。
データ連携で市民・企業双方が使える社会を目指す。
デジタル化の目的は「幸福度の向上」。
住み慣れた場所で健康に暮らし続けられることを支える仕組みを整備し、データを活用して幸福感を実現していく。
【金子議員の質問&意見】要点:市民生活に“データの見える化”を。三豊市版ウェルビーイングを指標に進める。
都会と肩を並べるためではなく、三豊市に足りない部分を補うためのデジタル化。
市民が健康で幸せに暮らすことが最終目的。データを整え、市民へ還元するための基盤整備に時間をかけて進める。
デジタル化は“目的ではなく手段”。幸福度を高めるための道具として推進していく。
【金子議員の意見】要点:デジタル万歳ではなく、「幸福のためのデジタル」。データ基盤整備を最優先に。
令和5年第4回定例会(第3日) 一般質問 【2023年12月07日】
国が掲げる構想は、デジタルを活用して地方の課題を解決し、地域の魅力を高める取組。
しかし三豊市の目指すデジタル化は、都会との格差をなくすことではなく、市民が住み慣れた場所で健康に、幸せを感じて暮らし続けられるようにするためのもの。
弱い部分をデジタルで補い、持続可能なまちをつくる視点で進める。
・AI人材育成拠点「MAiZM」を設置し、香川高専詫間キャンパスからAIを学んだ学生がベンチャー企業2社を設立。
・教育現場ではオンライン授業やデジタル教育環境の整備を実施。
・地域通貨「MitoPay」導入により地域消費を促進、今後は健康ポイントなどの仕組みへ展開。
・介護MaaS、オンデマンドモビリティなど交通・福祉分野にもデジタル活用を広げている。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・MitoPay登録者数は6,490人(2022年8月末時点)。
・MAiZM起業者は現在学生本人のみで、雇用発生には至っていない。
国の「農業DX構想」に基づき、AI・IoT・ロボット技術導入で作業を効率化。
労働力不足・高齢化の課題を補い、データを活用した消費者志向の農業を進める。
地方の個性を生かした持続可能な田園づくりを目指す。
・スマート農業=省力化・自動化・機械導入による効率化
・デジタル農業=データ収集・共有により経営と品質を安定化
三豊市では両面を組み合わせた取組を推進中。無人車・ドローン導入なども進む。
【金子議員の質問&意見】要点:デジタル=効率化+データ共有。技術と知見の融合で持続的な地域農業へ。
・交付率:42.43%(2022年8月時点)
・窓口キオスク端末導入を準備中(記入不要で証明書発行)。
・引越しワンストップサービス(2023年2月開始予定)で転出入手続をオンライン化。
・出張申請・休日開庁・商業施設での受付など普及活動を継続。
・カード取得が目的ではなく、市民サービス向上のために活用策を検討中。
【金子議員の質問&意見】要点:利便性向上に重点。オンライン化・出張対応で交付率アップを図る。
鶴岡サイエンスパークは産官学民が連携した成功例。
香川県にも高松空港跡地の「インテリジェントパーク」があり、類似の取組が進んでいる。
コロナ禍で働き方や研究の在り方が変化する中、デジタル×田園による新たな産業立地を検討する。
【金子議員の質問&意見】要点:産学官+市民連携による「三豊版サイエンスパーク」構想を視野に。
世代を超えたデータ活用は重要。国の基盤構築を踏まえ、三豊市独自のデータ集積と利活用を検討。
データ連携で市民・企業双方が使える社会を目指す。
デジタル化の目的は「幸福度の向上」。
住み慣れた場所で健康に暮らし続けられることを支える仕組みを整備し、データを活用して幸福感を実現していく。
【金子議員の質問&意見】要点:市民生活に“データの見える化”を。三豊市版ウェルビーイングを指標に進める。
都会と肩を並べるためではなく、三豊市に足りない部分を補うためのデジタル化。
市民が健康で幸せに暮らすことが最終目的。データを整え、市民へ還元するための基盤整備に時間をかけて進める。
デジタル化は“目的ではなく手段”。幸福度を高めるための道具として推進していく。
【金子議員の意見】要点:デジタル万歳ではなく、「幸福のためのデジタル」。データ基盤整備を最優先に。
令和7年第2回定例会(第2日) 一般質問 【2025年06月13日】
・新技術(SNS/生成AI等)は不可逆で、市民の情報取得行動に定着。行政も多様な媒体を到達度重視で併用。
・市の発信手段:広報紙・HP・防災行政無線・市公式LINE、毎月の記者懇談会とプレスリリース。
・SNS(Facebook/X/Instagram/TikTok)でも市長自ら発信。テレビ・ラジオ等とSNSは相互に拡散。
・目的:認知→関心→参加の流れを作り、シビックプライド(誇り+参加意識)を醸成。
・平時からの継続発信は、誤情報対策・災害時の正確な一次情報発信の訓練にも資する。
・「オールドメディア」は業界一般の区分用語で、軽侮の意図はない。
・薬用作物栽培などは市長SNSで経過報告を継続中。
・一部施策は成果が長期(足の長い投資)。中間の可視化は課題と認識し、発信の到達度を高めつつ改善を図る。
【金子議員の質問&意見】要点:「発信」だけでなく、成果・結果の見える化を。父母ヶ浜のようにSNSの力を認めつつ、市民生活の実感に結びつく報道へ。
・放送波の想定到達:FM香川エリア人口約518万人。14–15時台の聴取率2–3%(18–49歳、2021年参考)→約10〜15万人へ同時到達の目安。
・令和6年度委託料:145万2,000円/年(月2回×24回)。
・内容内訳:事業者出演10・祭り/イベント告知3・観光交流局1・市長3・職員施策PR7。
・狙い:一度に広域へ情報到達させ、市への認知→参画を促進。
・「誘導」懸念について:市政の理解促進を目的としており、恣意的な誘導を意図せず。ご意見は真摯に受け止める。
・取材誘致も重視。一方、能動的発信がなければ露出は安定しない。
・市民生活の支援策は別途推進中で、情報発信とトレードオフではない。
・番組の是非や配分は意見を踏まえ検討しつつ、効果とバランスを見極める。
【金子議員の質問&意見】要点:市外向け露出よりも、生活実感の向上と成果報告(出口)の定期発信を優先。税金投入の説明責任と、無料取材の最大化を提案。
令和7年教育民生常任委員会(第2回定例会付託案件部分)【2025年06月20日】
・県の委託事業として山本小学校で実施。
・「チーム山本」による、来てよかったと思える学校づくりを推進。
・内容:①友達のよさを認め合い自分のよさに気づく活動、②心のSOSの早期発見・早期対応、③不登校の未然防止に資する魅力ある学校づくり。
・主な実施:講師派遣研修、リーフレット作成。
・御意見を踏まえ、研修内容と周知物の実効性を重視して進める。
令和7年第4回定例会 一般質問 【2025年12月05日】
・国内カロリーベース食料自給率は38%(R5)、香川県は34%(麺文化による米消費減)。
・県内の水稲作付面積は10年前と比べ約3割減少。
・米価はH25~R5まで横ばいだったが、R6産は在庫減により高騰(全銘柄平均25,927円/60kg)。
・価格上昇は作付拡大・継続意欲を後押し。
・R6より21地区で地域計画づくりを進め、世代継承を図る。
・三豊は多品目・高品質が強み。AI・スマート農業で収量安定・省力化を進め、稼げる農業へ転換する。
・圃場整備率:H19末 45.2% → R4末 51.0%(+5.8pt、約20ha進捗)。
・合意形成や換地処分に時間と労力を要するが、県事業として着実に進行。
・補助率引き上げも追い風となり、計画的に整備を強化。
・R5改正の農業経営基盤強化促進法により制度化。
・旧小学校区を基準に、21地区で座談会を開催。
・地域ごとに農地の将来像・担い手を話し合い、合意形成を進めている。
令和5年第1回定例会(第3日)一般質問 【2023年03月08日】
令和5年第2回定例会(第2日) 一般質問 【2023年06月09日】
国が掲げる構想は、デジタルを活用して地方の課題を解決し、地域の魅力を高める取組。
しかし三豊市の目指すデジタル化は、都会との格差をなくすことではなく、市民が住み慣れた場所で健康に、幸せを感じて暮らし続けられるようにするためのもの。
弱い部分をデジタルで補い、持続可能なまちをつくる視点で進める。
・AI人材育成拠点「MAiZM」を設置し、香川高専詫間キャンパスからAIを学んだ学生がベンチャー企業2社を設立。
・教育現場ではオンライン授業やデジタル教育環境の整備を実施。
・地域通貨「MitoPay」導入により地域消費を促進、今後は健康ポイントなどの仕組みへ展開。
・介護MaaS、オンデマンドモビリティなど交通・福祉分野にもデジタル活用を広げている。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・MitoPay登録者数は6,490人(2022年8月末時点)。
・MAiZM起業者は現在学生本人のみで、雇用発生には至っていない。
国の「農業DX構想」に基づき、AI・IoT・ロボット技術導入で作業を効率化。
労働力不足・高齢化の課題を補い、データを活用した消費者志向の農業を進める。
地方の個性を生かした持続可能な田園づくりを目指す。
・スマート農業=省力化・自動化・機械導入による効率化
・デジタル農業=データ収集・共有により経営と品質を安定化
三豊市では両面を組み合わせた取組を推進中。無人車・ドローン導入なども進む。
【金子議員の質問&意見】要点:デジタル=効率化+データ共有。技術と知見の融合で持続的な地域農業へ。
・交付率:42.43%(2022年8月時点)
・窓口キオスク端末導入を準備中(記入不要で証明書発行)。
・引越しワンストップサービス(2023年2月開始予定)で転出入手続をオンライン化。
・出張申請・休日開庁・商業施設での受付など普及活動を継続。
・カード取得が目的ではなく、市民サービス向上のために活用策を検討中。
【金子議員の質問&意見】要点:利便性向上に重点。オンライン化・出張対応で交付率アップを図る。
鶴岡サイエンスパークは産官学民が連携した成功例。
香川県にも高松空港跡地の「インテリジェントパーク」があり、類似の取組が進んでいる。
コロナ禍で働き方や研究の在り方が変化する中、デジタル×田園による新たな産業立地を検討する。
【金子議員の質問&意見】要点:産学官+市民連携による「三豊版サイエンスパーク」構想を視野に。
世代を超えたデータ活用は重要。国の基盤構築を踏まえ、三豊市独自のデータ集積と利活用を検討。
データ連携で市民・企業双方が使える社会を目指す。
デジタル化の目的は「幸福度の向上」。
住み慣れた場所で健康に暮らし続けられることを支える仕組みを整備し、データを活用して幸福感を実現していく。
【金子議員の質問&意見】要点:市民生活に“データの見える化”を。三豊市版ウェルビーイングを指標に進める。
都会と肩を並べるためではなく、三豊市に足りない部分を補うためのデジタル化。
市民が健康で幸せに暮らすことが最終目的。データを整え、市民へ還元するための基盤整備に時間をかけて進める。
デジタル化は“目的ではなく手段”。幸福度を高めるための道具として推進していく。
【金子議員の意見】要点:デジタル万歳ではなく、「幸福のためのデジタル」。データ基盤整備を最優先に。
令和5年第3回定例会(第2日) 一般質問 【2023年09月07日】
国が掲げる構想は、デジタルを活用して地方の課題を解決し、地域の魅力を高める取組。
しかし三豊市の目指すデジタル化は、都会との格差をなくすことではなく、市民が住み慣れた場所で健康に、幸せを感じて暮らし続けられるようにするためのもの。
弱い部分をデジタルで補い、持続可能なまちをつくる視点で進める。
・AI人材育成拠点「MAiZM」を設置し、香川高専詫間キャンパスからAIを学んだ学生がベンチャー企業2社を設立。
・教育現場ではオンライン授業やデジタル教育環境の整備を実施。
・地域通貨「MitoPay」導入により地域消費を促進、今後は健康ポイントなどの仕組みへ展開。
・介護MaaS、オンデマンドモビリティなど交通・福祉分野にもデジタル活用を広げている。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・MitoPay登録者数は6,490人(2022年8月末時点)。
・MAiZM起業者は現在学生本人のみで、雇用発生には至っていない。
国の「農業DX構想」に基づき、AI・IoT・ロボット技術導入で作業を効率化。
労働力不足・高齢化の課題を補い、データを活用した消費者志向の農業を進める。
地方の個性を生かした持続可能な田園づくりを目指す。
・スマート農業=省力化・自動化・機械導入による効率化
・デジタル農業=データ収集・共有により経営と品質を安定化
三豊市では両面を組み合わせた取組を推進中。無人車・ドローン導入なども進む。
【金子議員の質問&意見】要点:デジタル=効率化+データ共有。技術と知見の融合で持続的な地域農業へ。
・交付率:42.43%(2022年8月時点)
・窓口キオスク端末導入を準備中(記入不要で証明書発行)。
・引越しワンストップサービス(2023年2月開始予定)で転出入手続をオンライン化。
・出張申請・休日開庁・商業施設での受付など普及活動を継続。
・カード取得が目的ではなく、市民サービス向上のために活用策を検討中。
【金子議員の質問&意見】要点:利便性向上に重点。オンライン化・出張対応で交付率アップを図る。
鶴岡サイエンスパークは産官学民が連携した成功例。
香川県にも高松空港跡地の「インテリジェントパーク」があり、類似の取組が進んでいる。
コロナ禍で働き方や研究の在り方が変化する中、デジタル×田園による新たな産業立地を検討する。
【金子議員の質問&意見】要点:産学官+市民連携による「三豊版サイエンスパーク」構想を視野に。
世代を超えたデータ活用は重要。国の基盤構築を踏まえ、三豊市独自のデータ集積と利活用を検討。
データ連携で市民・企業双方が使える社会を目指す。
デジタル化の目的は「幸福度の向上」。
住み慣れた場所で健康に暮らし続けられることを支える仕組みを整備し、データを活用して幸福感を実現していく。
【金子議員の質問&意見】要点:市民生活に“データの見える化”を。三豊市版ウェルビーイングを指標に進める。
都会と肩を並べるためではなく、三豊市に足りない部分を補うためのデジタル化。
市民が健康で幸せに暮らすことが最終目的。データを整え、市民へ還元するための基盤整備に時間をかけて進める。
デジタル化は“目的ではなく手段”。幸福度を高めるための道具として推進していく。
【金子議員の意見】要点:デジタル万歳ではなく、「幸福のためのデジタル」。データ基盤整備を最優先に。
令和5年第4回定例会(第3日) 一般質問 【2023年12月07日】
国が掲げる構想は、デジタルを活用して地方の課題を解決し、地域の魅力を高める取組。
しかし三豊市の目指すデジタル化は、都会との格差をなくすことではなく、市民が住み慣れた場所で健康に、幸せを感じて暮らし続けられるようにするためのもの。
弱い部分をデジタルで補い、持続可能なまちをつくる視点で進める。
・AI人材育成拠点「MAiZM」を設置し、香川高専詫間キャンパスからAIを学んだ学生がベンチャー企業2社を設立。
・教育現場ではオンライン授業やデジタル教育環境の整備を実施。
・地域通貨「MitoPay」導入により地域消費を促進、今後は健康ポイントなどの仕組みへ展開。
・介護MaaS、オンデマンドモビリティなど交通・福祉分野にもデジタル活用を広げている。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・MitoPay登録者数は6,490人(2022年8月末時点)。
・MAiZM起業者は現在学生本人のみで、雇用発生には至っていない。
国の「農業DX構想」に基づき、AI・IoT・ロボット技術導入で作業を効率化。
労働力不足・高齢化の課題を補い、データを活用した消費者志向の農業を進める。
地方の個性を生かした持続可能な田園づくりを目指す。
・スマート農業=省力化・自動化・機械導入による効率化
・デジタル農業=データ収集・共有により経営と品質を安定化
三豊市では両面を組み合わせた取組を推進中。無人車・ドローン導入なども進む。
【金子議員の質問&意見】要点:デジタル=効率化+データ共有。技術と知見の融合で持続的な地域農業へ。
・交付率:42.43%(2022年8月時点)
・窓口キオスク端末導入を準備中(記入不要で証明書発行)。
・引越しワンストップサービス(2023年2月開始予定)で転出入手続をオンライン化。
・出張申請・休日開庁・商業施設での受付など普及活動を継続。
・カード取得が目的ではなく、市民サービス向上のために活用策を検討中。
【金子議員の質問&意見】要点:利便性向上に重点。オンライン化・出張対応で交付率アップを図る。
鶴岡サイエンスパークは産官学民が連携した成功例。
香川県にも高松空港跡地の「インテリジェントパーク」があり、類似の取組が進んでいる。
コロナ禍で働き方や研究の在り方が変化する中、デジタル×田園による新たな産業立地を検討する。
【金子議員の質問&意見】要点:産学官+市民連携による「三豊版サイエンスパーク」構想を視野に。
世代を超えたデータ活用は重要。国の基盤構築を踏まえ、三豊市独自のデータ集積と利活用を検討。
データ連携で市民・企業双方が使える社会を目指す。
デジタル化の目的は「幸福度の向上」。
住み慣れた場所で健康に暮らし続けられることを支える仕組みを整備し、データを活用して幸福感を実現していく。
【金子議員の質問&意見】要点:市民生活に“データの見える化”を。三豊市版ウェルビーイングを指標に進める。
都会と肩を並べるためではなく、三豊市に足りない部分を補うためのデジタル化。
市民が健康で幸せに暮らすことが最終目的。データを整え、市民へ還元するための基盤整備に時間をかけて進める。
デジタル化は“目的ではなく手段”。幸福度を高めるための道具として推進していく。
【金子議員の意見】要点:デジタル万歳ではなく、「幸福のためのデジタル」。データ基盤整備を最優先に。
⇒ 2024年度 議会活動
2024年度は副議長を担当のため質問・意見陳述はありません。
⇒ 2023年度 議会活動
令和5年第1回定例会(第3日)一般質問 【2023年03月08日】
・住民税非課税世帯等へ臨時特別給付金(R3・R4実施、1世帯10万円)。
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(10/25専決、1世帯5万円)。
・住居確保給付金、生活困窮者自立支援金、社協の特例貸付(~9月末)等を実施。
・就労支援員・主任相談員を配置し、就労相談や家計改善支援を継続。
・国の重点支援地方交付金(上限1億9,093万8,000円)を活用し、8事業の補正を提出。
・可能な限りプッシュ型で給付。
・周知は広報・HP・防災無線・SNS・LINEを基本に、独居高齢者等には社協・民生委員・SW等と連携して情報把握→支援へ接続。
・申請受付は終了。今後の国の新メニューが出次第、迅速に周知・接続します。
・一律施策は難しいが、ケース毎に最適支援を検討。
・相談が届きにくい世帯へも、アプローチ型(こちらから出向く)で対応。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・香川県では県道路異常通報システムを2022/8/1から運用。
・利点:位置情報・写真で現場把握が迅速=初動短縮・事故抑止。通報機会も拡大。
・緊急案件(陥没・倒木等)は電話通報が重要。
・本市でもLINE公式の活用を含め、費用対効果や先進事例を踏まえて関係部局と協議・研究。
・施設全般への展開は市民利便が高い。
・県の利用状況(毎月30件台の通報)も参考に、総合窓口型の設計可否を検討。
・項目が増えるほど配分・所管整理が必要=部局横断で議論。
・先進自治体の方式・運用負荷・費用を比較研究。
・職員の負担軽減効果も踏まえ、導入を前向きに検討。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
令和5年第2回定例会(第2日) 一般質問 【2023年06月09日】
国が掲げる構想は、デジタルを活用して地方の課題を解決し、地域の魅力を高める取組。
しかし三豊市の目指すデジタル化は、都会との格差をなくすことではなく、市民が住み慣れた場所で健康に、幸せを感じて暮らし続けられるようにするためのもの。
弱い部分をデジタルで補い、持続可能なまちをつくる視点で進める。
・AI人材育成拠点「MAiZM」を設置し、香川高専詫間キャンパスからAIを学んだ学生がベンチャー企業2社を設立。
・教育現場ではオンライン授業やデジタル教育環境の整備を実施。
・地域通貨「MitoPay」導入により地域消費を促進、今後は健康ポイントなどの仕組みへ展開。
・介護MaaS、オンデマンドモビリティなど交通・福祉分野にもデジタル活用を広げている。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・MitoPay登録者数は6,490人(2022年8月末時点)。
・MAiZM起業者は現在学生本人のみで、雇用発生には至っていない。
国の「農業DX構想」に基づき、AI・IoT・ロボット技術導入で作業を効率化。
労働力不足・高齢化の課題を補い、データを活用した消費者志向の農業を進める。
地方の個性を生かした持続可能な田園づくりを目指す。
・スマート農業=省力化・自動化・機械導入による効率化
・デジタル農業=データ収集・共有により経営と品質を安定化
三豊市では両面を組み合わせた取組を推進中。無人車・ドローン導入なども進む。
【金子議員の質問&意見】要点:デジタル=効率化+データ共有。技術と知見の融合で持続的な地域農業へ。
・交付率:42.43%(2022年8月時点)
・窓口キオスク端末導入を準備中(記入不要で証明書発行)。
・引越しワンストップサービス(2023年2月開始予定)で転出入手続をオンライン化。
・出張申請・休日開庁・商業施設での受付など普及活動を継続。
・カード取得が目的ではなく、市民サービス向上のために活用策を検討中。
【金子議員の質問&意見】要点:利便性向上に重点。オンライン化・出張対応で交付率アップを図る。
鶴岡サイエンスパークは産官学民が連携した成功例。
香川県にも高松空港跡地の「インテリジェントパーク」があり、類似の取組が進んでいる。
コロナ禍で働き方や研究の在り方が変化する中、デジタル×田園による新たな産業立地を検討する。
【金子議員の質問&意見】要点:産学官+市民連携による「三豊版サイエンスパーク」構想を視野に。
世代を超えたデータ活用は重要。国の基盤構築を踏まえ、三豊市独自のデータ集積と利活用を検討。
データ連携で市民・企業双方が使える社会を目指す。
デジタル化の目的は「幸福度の向上」。
住み慣れた場所で健康に暮らし続けられることを支える仕組みを整備し、データを活用して幸福感を実現していく。
【金子議員の質問&意見】要点:市民生活に“データの見える化”を。三豊市版ウェルビーイングを指標に進める。
都会と肩を並べるためではなく、三豊市に足りない部分を補うためのデジタル化。
市民が健康で幸せに暮らすことが最終目的。データを整え、市民へ還元するための基盤整備に時間をかけて進める。
デジタル化は“目的ではなく手段”。幸福度を高めるための道具として推進していく。
【金子議員の意見】要点:デジタル万歳ではなく、「幸福のためのデジタル」。データ基盤整備を最優先に。
令和5年第3回定例会(第2日) 一般質問 【2023年09月07日】
・人材の強みを生かす配置と役割分担を前提に、毎年度の人事異動を実施。
・職員研修計画に基づき、高度専門研修を推進。
・外部人材は国・県との人脈、新課題の加速に有効。ただし職員の意欲を損なわないよう役割・配置を適切に運用。
・外部人材“だけ”に依存せず、経験豊富な職員との協働で相乗効果。
・人事考課と自己申告書で専門志向・希望を把握(現部署での専門深化/他部署での専門志向など)。
・これらを総合判断し配置。心理的安全性の確保とエンゲージメント研修を継続。
・市民目線を重視し、現場を知る職員の知見と外部の新知見を組み合わせて判断・実施。
・目的は計画の完遂と市民サービス向上。そのための最善配置と職員の地力向上(研修・育成)を進める。
【金子議員の質問&意見】要点:市民・現場の目線を軸に、経験豊富な職員が花開く「任せて伸ばす」配置と、外部登用の役割明確化で組織力を最大化。
・事件を教訓化し、人権教育・啓発を推進。
・SNSでのデマ拡散・誹謗中傷に対応し、正しい情報の見極めと行動を促す。
・多様性を認め合うまちを目指し、継続的に取組を展開。
・被害・加害双方へ長期的影響が及ぶことを再認識。
・事実に基づく検証・記録の継承を進め、学校・職場・地域での不断の人権学習により知識と人権感覚を育む。
・市長は出席できなかったが、市長部局として参加し学びを共有。
・内容を今後の啓発政策へ反映していく。
【金子議員の質問&意見】要点:100年の教訓を「知る」から「行動」へ。メディアリテラシー×人権学習を常設化し、差別や中傷が根付かない文化を次世代へ。
令和5年第4回定例会(第3日) 一般質問 【2023年12月07日】
・本市人口は合併時71,180人→2023/11/1推計58,939人へ減少。出生率も県動向から低下傾向と認識。
・子育て支援:子ども医療費助成を18歳到達後最初の3/31まで拡大。
・保育料:第2子半額/第3子以降無償。
・学校給食:2009年度以降据え置き、不足分は市財源で補填し栄養水準確保。
・文化・スポーツ:展示館の子ども無料区分、スポ少減免等。
・経済循環は稼ぐ力の強化+地域内消費が鍵。設備投資支援やMito Payで市内消費を促進。
・おむつ定期便は未実施だが、妊娠8か月面談(希望者)で保健師が関係性を構築し産後不安に伴走。
・第3子以降の保育料無償は所得制限なし(保育料自体は所得階層で設定)。
・子どもが安心・気軽に使える運用を検討。使用料の在り方も機会を捉えて見直し検討。
【金子議員の質問&意見】要点:市民が「使えるお金」を増やす設計を最優先。母親・当事者目線の無償化と伴走支援で人口・税収の好循環をつくる。
・産業分野では中小支援+Mito Payで消費拡大を推進。
・一過性でなく持続的な地域の稼ぐ力を高めるのが目的。
・国の交付金動向も踏まえつつ、市独自課題に即した施策を提案・実施。
・基礎自治体として地域の声を踏まえた即応策を検討・上程中(低所得者・ひとり親等への独自交付)。
・Mito Pay:30%プレミアムを年2回実施。チャージ約3億円+プレミアム1億円=計4億円が市内循環。
・延べ約1.1万人が利用。デジタル普及員による高齢者講座で裾野拡大。
【金子議員の質問&意見】要点:全市民型・所得制限なしの施策で波及効果を最大化。地域通貨は有効だが、現金同等の即効策も組み合わせて家計を下支え。
・先に示した耕作放棄地増加率は約5%増に訂正。
・市内山林約7,800ha、うち約5,200haがクヌギ・ナラ等の雑木林。
・腐葉土は通気・保肥・保水に優れ、化学肥料低減にも寄与。
・おろ活用×山林整備の循環モデルは有望。関係機関と検討を進める。
・山×農地の相乗効果により経済循環を創出できるよう、部局横断で実行性ある設計を協議。
・策定中の農業振興計画に、議員指摘の視点も反映検討。
【金子議員の質問&意見】要点:「山から田へ」資源循環で土を再生し、もうかる農業へ。行政が旗を振り、山林整備・土づくり・販路までをつなぐ。
⇒ 2022年度 議会活動
令和4年第1回定例会(第4日)一般質問 【2022年03月15日】
令和4年第2回定例会(第2日)一般質問 【2022年06月13日】
空き家バンクは約90件登録、うち約2割が農地情報付き。
地域再生法の新制度で下限面積緩和の特例あり。県内実施例はまだなく、関係部局連携で制度研究を進める。
家庭菜園・就農ニーズを把握し関係課と連携。移住サイト「みとよ暮らし手帳」で住まい・農業情報やイベントを発信。
オンライン相談と地域団体との協働を強化。
義務教育機会確保法に基づき学び直しの場として必要。
外国籍中長期在留者は約1,000人(上位:ベトナム・中国・ミャンマー・フィリピン・インドネシア)。
希望把握のアンケート実施中。結果を基に設置形態・人員・カリキュラム等を検討。
西讃で学びの場を設ければ近隣市町からの参加も可能。
外国人のみの施設ではなく、未修了者・不登校生徒等も対象。
ICT活用は併用するが、日本語教育のみのオンライン施策とは切り分けて検討。
卒業資格は夜間中学校(分教室等含む)として設置すれば付与可能。
令和2年1–10月の自殺者12人(男女各6、70代中心)。全国同様に女性増傾向。
自殺対策計画に基づき、相談窓口周知・人材育成・ネットワーク強化を推進。
学校では自殺予防教育、SC/SSW連携で早期発見と支援を徹底。
令和4年第3回定例会(第2日)一般質問 【2022年09月07日】
国が掲げる構想は、デジタルを活用して地方の課題を解決し、地域の魅力を高める取組。
しかし三豊市の目指すデジタル化は、都会との格差をなくすことではなく、市民が住み慣れた場所で健康に、幸せを感じて暮らし続けられるようにするためのもの。
弱い部分をデジタルで補い、持続可能なまちをつくる視点で進める。
・AI人材育成拠点「MAiZM」を設置し、香川高専詫間キャンパスからAIを学んだ学生がベンチャー企業2社を設立。
・教育現場ではオンライン授業やデジタル教育環境の整備を実施。
・地域通貨「MitoPay」導入により地域消費を促進、今後は健康ポイントなどの仕組みへ展開。
・介護MaaS、オンデマンドモビリティなど交通・福祉分野にもデジタル活用を広げている。
【金子議員の質問&意見】要点:都市と競うのではなく、地域の弱点を補う“持続のためのデジタル化”を推進。
・MitoPay登録者数は6,490人(2022年8月末時点)。
・MAiZM起業者は現在学生本人のみで、雇用発生には至っていない。
国の「農業DX構想」に基づき、AI・IoT・ロボット技術導入で作業を効率化。
労働力不足・高齢化の課題を補い、データを活用した消費者志向の農業を進める。
地方の個性を生かした持続可能な田園づくりを目指す。
・スマート農業=省力化・自動化・機械導入による効率化
・デジタル農業=データ収集・共有により経営と品質を安定化
三豊市では両面を組み合わせた取組を推進中。無人車・ドローン導入なども進む。
【金子議員の質問&意見】要点:デジタル=効率化+データ共有。技術と知見の融合で持続的な地域農業へ。
・交付率:42.43%(2022年8月時点)
・窓口キオスク端末導入を準備中(記入不要で証明書発行)。
・引越しワンストップサービス(2023年2月開始予定)で転出入手続をオンライン化。
・出張申請・休日開庁・商業施設での受付など普及活動を継続。
・カード取得が目的ではなく、市民サービス向上のために活用策を検討中。
【金子議員の質問&意見】要点:利便性向上に重点。オンライン化・出張対応で交付率アップを図る。
鶴岡サイエンスパークは産官学民が連携した成功例。
香川県にも高松空港跡地の「インテリジェントパーク」があり、類似の取組が進んでいる。
コロナ禍で働き方や研究の在り方が変化する中、デジタル×田園による新たな産業立地を検討する。
【金子議員の質問&意見】要点:産学官+市民連携による「三豊版サイエンスパーク」構想を視野に。
世代を超えたデータ活用は重要。国の基盤構築を踏まえ、三豊市独自のデータ集積と利活用を検討。
データ連携で市民・企業双方が使える社会を目指す。
デジタル化の目的は「幸福度の向上」。
住み慣れた場所で健康に暮らし続けられることを支える仕組みを整備し、データを活用して幸福感を実現していく。
【金子議員の質問&意見】要点:市民生活に“データの見える化”を。三豊市版ウェルビーイングを指標に進める。
都会と肩を並べるためではなく、三豊市に足りない部分を補うためのデジタル化。
市民が健康で幸せに暮らすことが最終目的。データを整え、市民へ還元するための基盤整備に時間をかけて進める。
デジタル化は“目的ではなく手段”。幸福度を高めるための道具として推進していく。
【金子議員の意見】要点:デジタル万歳ではなく、「幸福のためのデジタル」。データ基盤整備を最優先に。
令和4年第4回定例会(第4日)一般質問 【2022年12月09日】
・住民税非課税世帯等へ10万円/世帯(R3・R4実施)。
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として5万円/世帯(10/25専決、支給開始)。
・住居確保給付金、生活困窮者自立支援、社協の特例貸付(受付は9月末で終了)。
・国の重点支援地方交付金:本市限度額1億9,093万8,000円。
・対策8事業の増額補正を12月議会へ。
・国動向を注視しつつ、長期影響を見定め、必要な支援を検討・実施。
・可能な限りプッシュ型で負担軽減。ただし全て無申請は困難。
・広報、HP、防災無線、SNS/LINEで周知。
・民生委員・社協・SW等と連携し、独居高齢者等の漏れを最小化。
・特例貸付は9月末で受付終了。
・新たな国施策が出れば速やかに周知・接続。
・全戸一律の恒久策は難しいが、アプローチ型(出向く相談)も活用し寄り添い対応。
・香川県道路異常通報システム(8/1開始、月30件台)を確認済。
・本市は現状電話中心(一部メール)。迅速対応・事故抑止に有効と認識。
・大規模陥没等の緊急案件は電話併用が必要。
・本市公式LINE等の活用も視野に、費用対効果と留意点を整理し導入可能性を研究。
・施設横断の受付は利便性向上につながる。
・所管配分や運用設計を要するため、県の運用や先進事例を踏まえ、前向きに検討。
・職員負担軽減の観点も含め、導入前提で具体検討を進める。
・年末年始を見据え、周知・伴走支援を強化。
・通報システムは運用設計・費用対効果を詰め、導入に向けて前向きに検討。
⇒ 2021年度 議会活動
令和3年第1回定例会(第4日)一般質問 【2021年03月10日】
※ 議員からは「圃場整備を土台に、野菜の王道を適地適作・タイミング供給で“稼ぎに行く”農業へ」との提起。
令和3年第2回定例会(第2日)一般質問 【2021年06月15日】
※ 金子議員からは「透明化」「次世代への権限委譲・信頼」重視の提起。
※ 金子議員からは「観光再生を“定住増”に結び付ける中長期(3〜10年)視点」を要請。部長は重点強化に前向きと回答。
令和3年第3回定例会(第2日)一般質問 【2021年09月06日】
●背景:漢方製剤市場は直近5年で+18.7%、国内生産額 約2,000億円。生薬は約9割輸入依存で価格上昇。
●狙い:国産化と安定供給に寄与しつつ、遊休農地活用・所得増・人材育成・福祉連携へ。
●当面目標(早期):ミシマサイコ 10ha/トウキ 3ha/キジツ 10ha。将来的に産地化・農業法人も選択肢。
●基幹従事者:就農ハードルを踏まえ、担い手支援(機械施設導入、新規就農・規模拡大、集落営農・共同機械)を推進。
●所得目標:認定農業者はまず年収350万円を目安に向上支援。
●方針:薬用作物は主幹ではなく「プラスアルファ」。主力(米麦・レタス・ブロッコリー等)は継続強化。作付補助は行わず、技術支援と経営・集積・機械等を後押し。
●補助金は不実施(栽培段階)。技術支援のみ。
●香川の強みは「たくみの技=手間をかけて品質で勝つ」。国産薬用は単価が高く、反収収益の向上余地あり。
●インフラ:農道・水路・集積・機械等の経営基盤整備を重視。
●出口:トップセールス等の販路支援で生産〜販売を接続。
●超中長期:10〜20年スパンで三豊の自然・条件を精査し、やる気ある生産者が稼げる環境を整える。
金子議員側の主張:主幹作物の収益改善が要。認定農業者「350万」では魅力不足、700万〜1,000万も狙える環境設計を求める。
●方式:三豊市×観音寺市の共同採択。教科ごとに調査員選任→調査委員会×2→選定協議会(10名)→各教育委員会で決定。
●体制:調査員は小学校採択で78名(R1)、中学校で52名(R2)。
●主な評価点:興味関心喚起、探究の道筋、地域学習への工夫、年表とキーワードで流れを把握、基礎定着の設問等。
●考え方:検定を通った教科書は現時点で国が可としたもの。多様な学説を踏まえつつ、学習指導要領の目標(歴史的見方・国際社会の公民資質)達成に資するものを厳正採択。今後も公正・適正に。
金子議員側の主張:自国の歴史に誇りを持てる内容か精査を。ネット時代の史料充実を踏まえ、次回採択での更なる検証を要望。
●即応:事故翌日に全校へ再点検と指導徹底を通知。
●点検:国の合同点検要領で8月に危険箇所調査(交通+防犯・防災視点)。
段階1:学校把握情報→関係機関確認/段階2:PTA等の意見集約。
●連携体制:総務課(事務局)/教育委員会/建設港湾課/土地改良課/三豊警察/国交省善通寺維持出張所/県西讃土木事務所。
●施策:ソフト(注意喚起、見守り)+ハード(グリーンベルト等)。ただし拡幅・蓋掛けは費用・時間制約。
●運用:所管単独で即応可の案件は迅速実施、連携が要る箇所は合同点検で効果的対策。情報共有で処理を平準化。
●専横断チーム化:現組織での連携のスピード向上を図る(配置は今後も改善検討)。
金子議員側の主張:長年未解決の箇所もある。特別チーム等で更なる迅速化を。
令和3年第4回定例会(第2日)一般質問 【2021年12月03日】
※ 金子議員からは「透明化」「次世代への権限委譲・信頼」重視の提起。
※ 金子議員からは「観光再生を“定住増”に結び付ける中長期(3〜10年)視点」を要請。部長は重点強化に前向きと回答。
⇒ 2020年度 議会活動
令和2年第3回定例会(第2日)一般質問 【2020年09月08日】
オンライン申請は583件、受理503件、不備80件(13.7%)。主因は世帯主以外からの申請。市内で大きな混乱はなし。
独自利用は現状コンビニ交付のみ。印鑑登録証・図書カード・罹災証明での活用は未実施で、利便性や他市動向を踏まえ検討。
普及は増加傾向:昨年度申請2,274枚→本年度(4–8/23)2,688枚(申請率21.29%)。交付は昨年度1,891枚→本年度5か月で1,956枚(交付率17.77%)。
印鑑証明はマイナカードでコンビニ交付(6:30–23:00)が可能。窓口でカードのみ提示では発行不可。混雑緩和のためコンビニ交付の周知を継続。
導入年取得率0.67%→直近2.46%(約3.6倍)。今年4–7月は419件(住民票40%/戸籍30%/印鑑証明27%/戸籍附票3%)。県外取得27%。
令和元年10月に見直し:市単独補助は事業費20〜120万円に対し65%補助。原材料等支給は原材料費上限30万円・機械借上料上限15万円。
規模の大きい案件は国県補助事業を採用。制度は見直し初年度のため、直ちに再改定は困難。緊急箇所は部分改修+長期計画で対応。多面的機能支援交付金も活用。
多面的機能支払制度の資源向上交付金で長寿命化の補修・更新を支援(原則一件200万円未満。計画策定で200万円以上も可)。市・県審査を経て実施。地域協働で保全管理を推進。
県内8市で要件や枠組みが大きく異なり一概比較不可。単県補助の要件緩和や多面的機能制度への誘導、市単独制度の有無など差異があるため、本市は活用状況を見極めつつ運用。
旧高瀬町からの交流を継承し、平成19年に協定締結。令和2年に国際交流協会発足。
多文化共生と国際感覚醸成の観点から、時代に合わせ内容を見直しつつ、交流は継続・発展の方針。市民・民間団体・事業者による相互に益のある交流環境を整備。
「こんなときだからこそ」自治体間交流を。協会と連携し、国際感覚ある人材育成と対等な共存関係の構築を目指し、発展的継続が適当。
困難な国家間関係を超え、実績で交流を維持・復活した事例もある。本市も未来志向で有益な交流となるよう継続し、目標に近づける取組を進める。
令和2年第4回定例会(第2日)一般質問 【2020年12月04日】
空き家バンクは約90件登録、うち約2割が農地情報付き。
地域再生法の新制度で下限面積緩和の特例あり。県内実施例はまだなく、関係部局連携で制度研究を進める。
家庭菜園・就農ニーズを把握し関係課と連携。移住サイト「みとよ暮らし手帳」で住まい・農業情報やイベントを発信。
オンライン相談と地域団体との協働を強化。
義務教育機会確保法に基づき学び直しの場として必要。
外国籍中長期在留者は約1,000人(上位:ベトナム・中国・ミャンマー・フィリピン・インドネシア)。
希望把握のアンケート実施中。結果を基に設置形態・人員・カリキュラム等を検討。
西讃で学びの場を設ければ近隣市町からの参加も可能。
外国人のみの施設ではなく、未修了者・不登校生徒等も対象。
ICT活用は併用するが、日本語教育のみのオンライン施策とは切り分けて検討。
卒業資格は夜間中学校(分教室等含む)として設置すれば付与可能。
令和2年1–10月の自殺者12人(男女各6、70代中心)。全国同様に女性増傾向。
自殺対策計画に基づき、相談窓口周知・人材育成・ネットワーク強化を推進。
学校では自殺予防教育、SC/SSW連携で早期発見と支援を徹底。
⇒ 2019年度 議会活動
⇒ 2018年度 議会活動
⇒ 2017年度 議会活動
⇒ 2016年度 議会活動
⇒ 2015年度 議会活動
⇒ 2014年度 議会活動
- 平成26年第4回定例会(第5日) 建設経済常任委員会報告 【2014.12.22】
- 平成26年第4回定例会(第4日) 一般質問 【2014.12.10】
- 平成26年第3回定例会(第6日) 建設経済常任委員会報告 【2014.09.26】
- 平成26年第3回定例会(第2日) 一般質問 【2014.09.10】
- 平成26年第2回定例会(第5日) 建設経済常任委員会報告 【2014.06.26】
- 平成26年第2回定例会(第5日) 意見書 趣旨説明 【2014.06.26】
- 平成26年第1回定例会(第5日) 建設経済常任委員会報告 【2014.03.28】
- 平成26年第1回定例会(第2日) 建設経済常任委員会報告 【2014.03.07】
⇒ 2013年度 議会活動
- 平成25年第4回定例会(第5日) 総務教育常任委員会報告 【2013.12.20】
- 平成25年第4回定例会(第2日) 一般質問 【2013.12.06】
- 平成25年第3回定例会(第6日) 総務教育常任委員会報告 【2013.09.26】
- 平成25年第3回定例会(第4日) 一般質問 【2013.09.12】
- 平成25年第3回臨時会(第1日) 総務教育常任委員会報告 【2013.07.29】
- 平成25年第2回定例会(第5日) 総務教育常任委員会報告 【2013.06.27】
- 平成25年第2回定例会(第4日) 一般質問 【2013.06.14】
- 平成25年第1回定例会(第5日) 総務教育常任委員会報告 【2013.03.28】